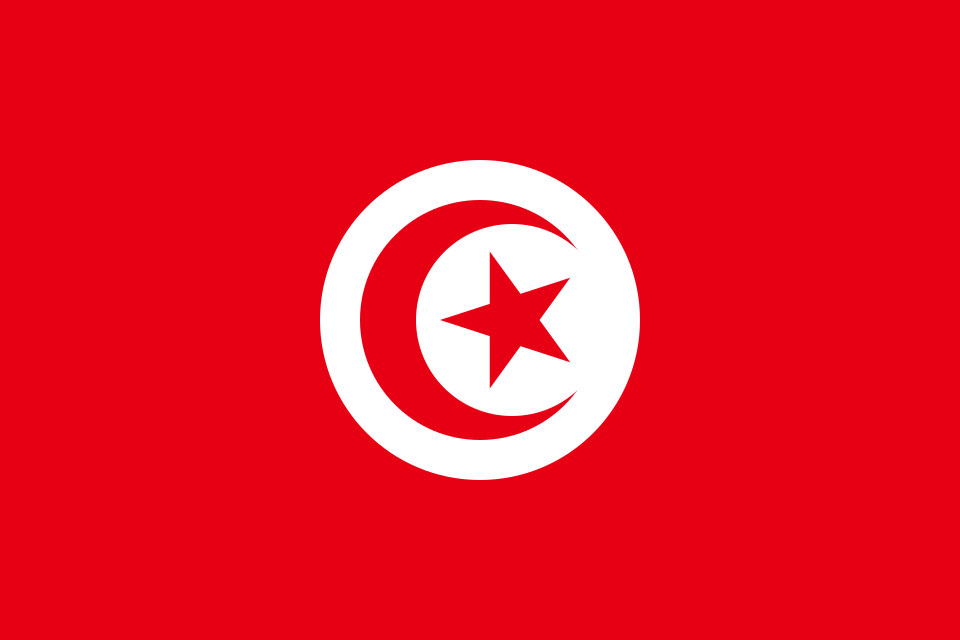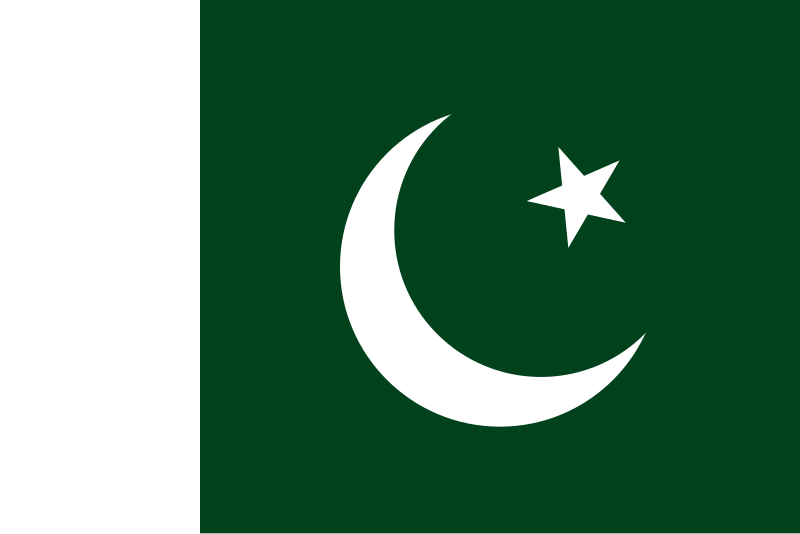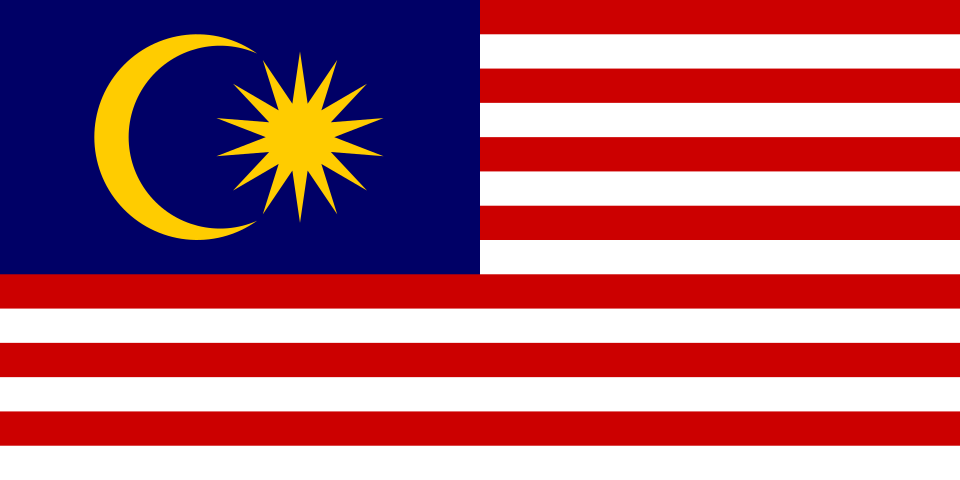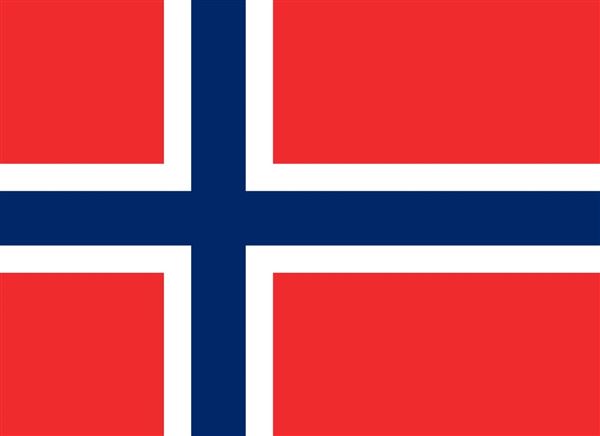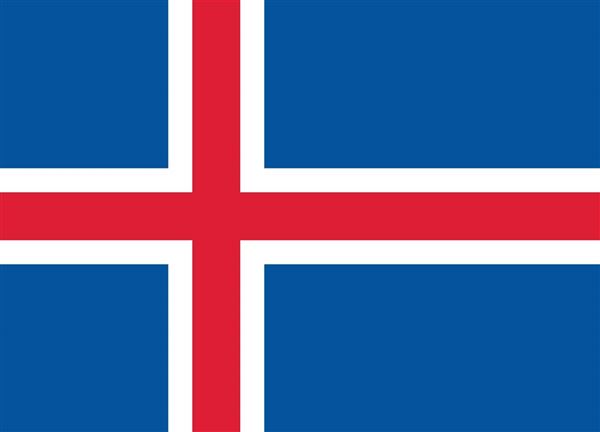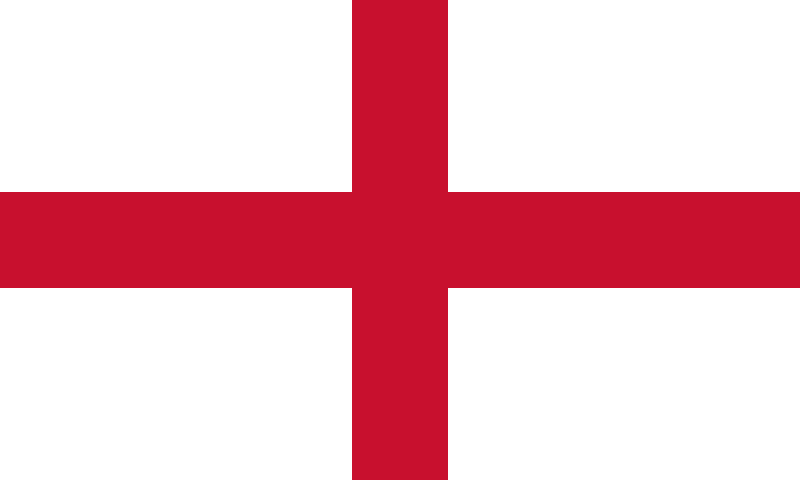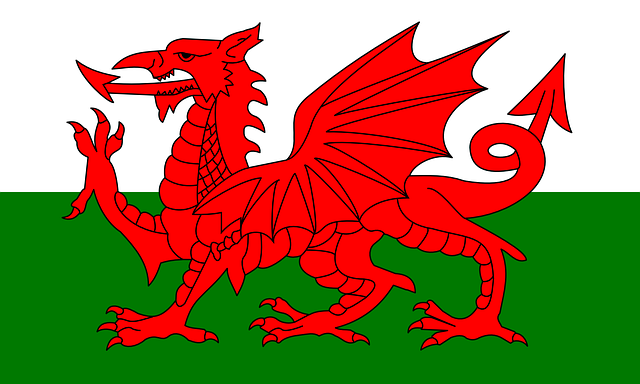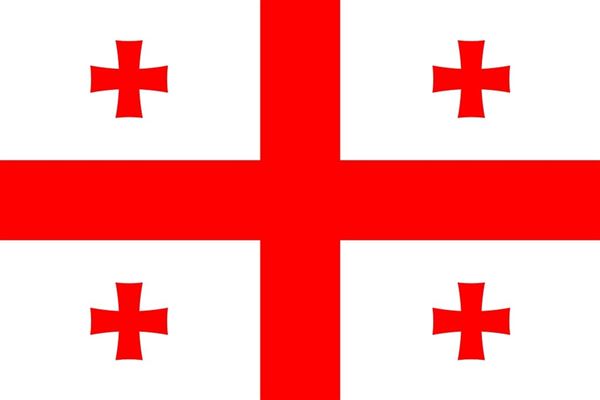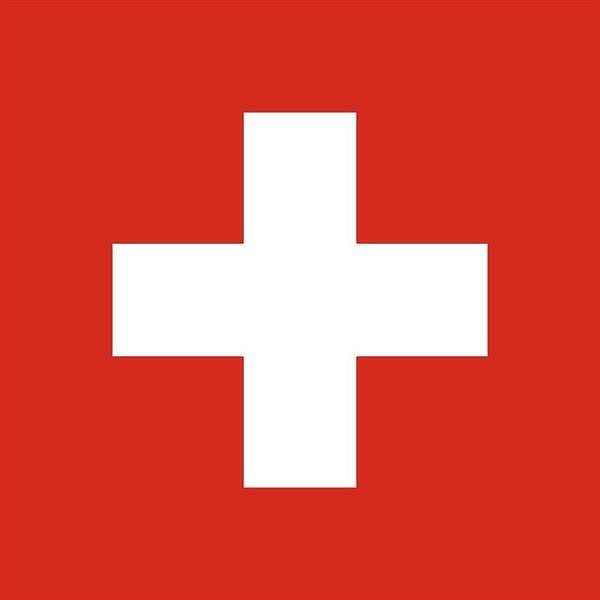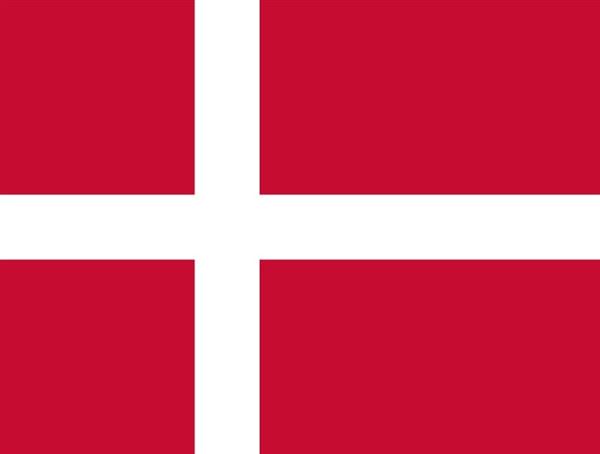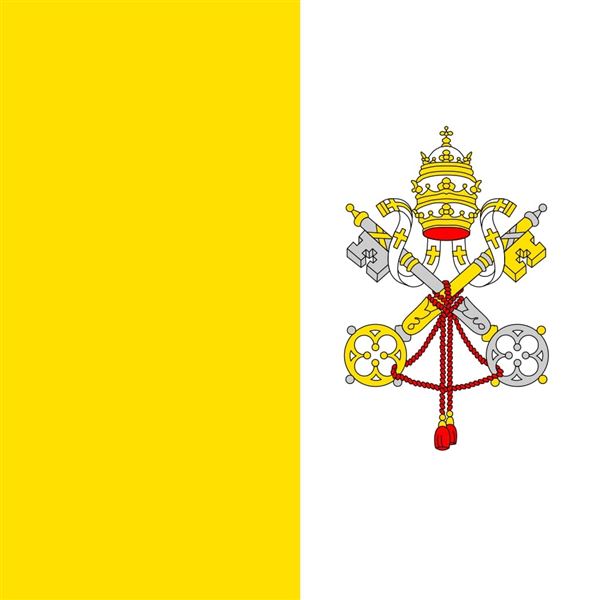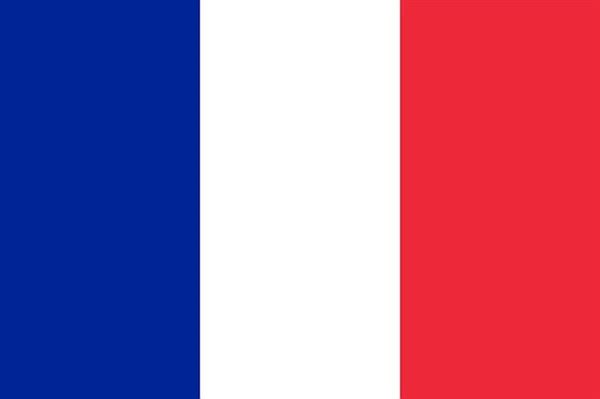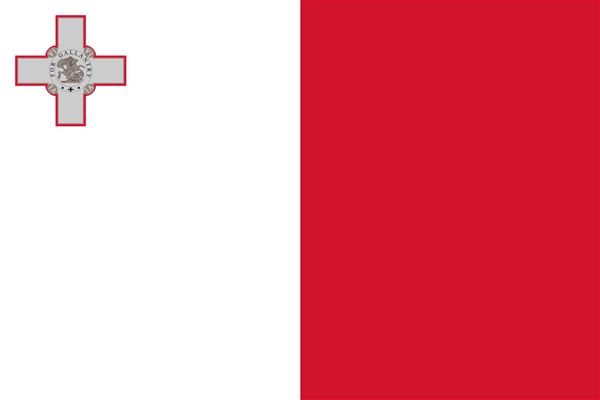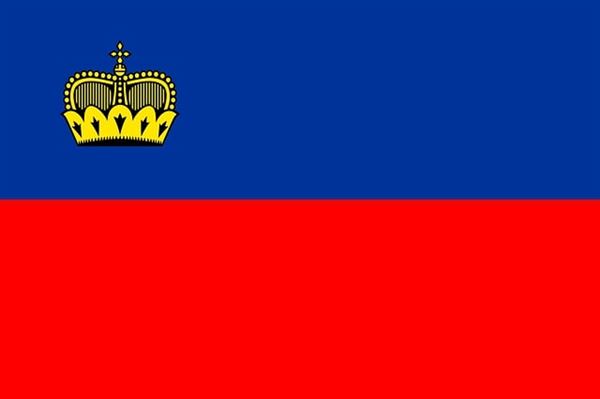トルコ国旗の由来&色の意味|信仰と戦いの歴史がにじむ三日月と星

トルコの国旗
|
国旗の基本情報 |
|
|---|---|
| 採用国 | Turkey(トルコ) |
| 採用年 | 1936年(現在の仕様を法制化) |
| 縦横比 | 2:3 |
| デザイン |
|
| 色の意味 |
|
| 備考 |
オスマン帝国時代の旗に起源を持ち、トルコ共和国として近代化された。 |
赤地に白い三日月と星――トルコの国旗って、シンプルだけどめちゃくちゃ存在感ありますよね。でもこのデザイン、ただ目立つってだけじゃないんです。そこには、トルコという国がたどってきた戦いの歴史とイスラムへの信仰が、ぎゅっと詰め込まれているんですよ。この記事では、トルコ国旗の色やシンボルの意味、似た旗との違い、そして国の成り立ちとどう関係してるのかをわかりやすく解説していきます!
トルコってどんな国?

トルコはヨーロッパとアジアの境目にある国で、イスタンブールなんかは「アジアとヨーロッパをまたぐ街」としても有名ですよね。位置的にも歴史的にも、いろんな文化が入り混じってきた超・交差点的な国なんです。
そして忘れちゃいけないのが、トルコはかつてオスマン帝国の中心だったこと。東ローマ帝国を滅ぼし、何世紀にもわたってヨーロッパや中東を支配した大帝国の後継者なんですよ。そんな背景もあって、トルコ国旗は帝国の誇りと信仰の象徴としての意味が強く込められています。
国旗デザインの意味・由来
トルコ国旗は、赤い背景に白い三日月と五芒星という超シンプルなデザイン。でも、それぞれの要素がめちゃくちゃ奥深いんです。
赤は血と戦い、そして祖国への犠牲
まず背景の赤色。これは、オスマン帝国の軍旗にも使われていた伝統的な色で、戦い・勇気・そして祖国のために流された血を象徴しています。
トルコでは、この赤を「祖国の大地に染み込んだ血の色」としてとらえる考え方もあるほど、国家への献身を強く意識した色なんですね。
三日月はイスラム世界の象徴
次に白い三日月。これはイスラム教のシンボルとしてよく知られてますが、トルコでは特にオスマン帝国時代から続く国家の印として大切にされてきました。
もともと三日月は古代から「夜を照らす光」「守護の力」を持つ神聖な形とされていて、それがイスラムの象徴として広がっていったんです。
星は国家とイスラムの一体性を示す
三日月のそばにある五芒星(星型)は、イスラムの「五行(信仰・礼拝・喜捨・断食・巡礼)」を示すとされることもあるし、国家の統一・独立を象徴するとも言われています。
つまりこの組み合わせは、「イスラムの信仰のもと、団結した国家が歩んでいく」――そんな理想のかたちを描いてるとも言えるんです。
似てる国旗
トルコの国旗と似ている旗は、やっぱりイスラム教を信仰する国々に多いんです。ただし、トルコ国旗のシンプルさと力強さは別格。色もモチーフも少ないぶん、メッセージがダイレクトに伝わるってところがポイントです。
国旗の変遷にみる国の歴史
トルコの国旗は、オスマン帝国時代から基本的なモチーフは変わっていないけど、細かいデザインや意味合いは時代とともに変化してきました。
オスマン帝国の軍旗として使われた赤
14世紀ごろから、オスマン帝国の軍隊は赤地に三日月のデザインを使っていました。当時はまだ星がついていなかったり、月の形も今より緩やかだったんです。
19世紀に現在の形に近づく
1839年、帝国の近代化を進める中で国旗としての規格化が行われ、赤地・白の三日月と星という基本形が定まりました。このころから星が月の内側に寄った位置に描かれるようになります。
共和国成立後もデザインは継続
1923年、オスマン帝国が滅亡してトルコ共和国が成立したあとも、この旗のデザインはそのまま引き継がれました。翌年の法律で星と月の正確な形や位置が決められ、いまの姿が完成するんです。
つまり、デザインは変わっていなくても、帝国から共和国へと国の形が変わっても「旗は変えなかった」――それくらい、トルコ人にとってこの旗は特別な存在なんですね。
まとめ:旗が伝えてくれるもの
トルコの国旗は、信仰・戦い・誇りの象徴です。赤は流された血と勇気、白の三日月はイスラムの信仰、星は国家としての誇りと統一。そのどれもが、歴史の中で何度も形を変えながらも生き残ってきた力を感じさせてくれます。
見た目はシンプルなのに、背後にあるストーリーは超濃厚。
この旗を見ると、トルコという国がどれだけ信念を持って歩んできたかが、じんわり伝わってくるんです。